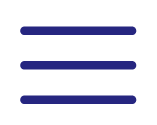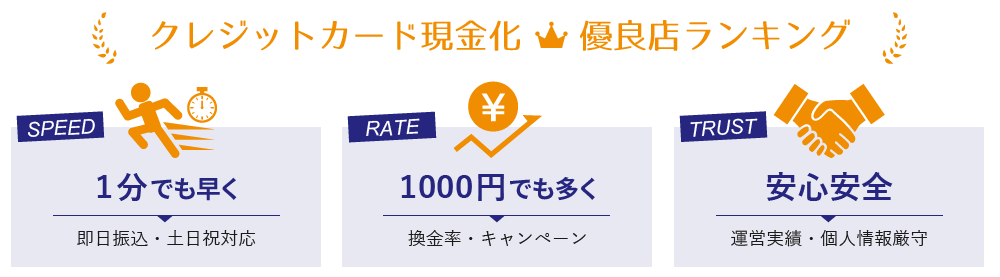クレジットカードの補償制度

クレジットカードは現金を持ち歩かずとも、対応した店舗であれば決済をすることができます。
支払いの際に小銭が出ないことや、ネットショッピングなどでも即時に代金を支払えるということもあり、非常に多くのメリットを持つ決済方法です。
お店によっては、暗証番号やサイン無しで決済できる点も、面倒がなく便利ですよね。
しかしそれほど手軽で便利なクレジットカードですが、もしも紛失や盗難してしまった場合、他人が自分のカードを手にすることになります。
そうなると、他人がすぐにカードが利用できる、と想像することができますよね。
そうした場合には、泣き寝入りをしてカードの持ち主が料金の支払いをするしかないのでしょうか?
安心の補償制度

実はクレジットカードには安心の補償制度があり、そうした紛失や盗難の場合の支払いを補償してくれるのです。
補償制度はカード会社によって多少の違いはありますが、原則として「盗難や紛失などの際に不正に使用された支払いは、持ち主に支払いの義務は無い」といったものになっています。
補償制度を利用するためには?
身に覚えのない請求などにより不正利用が疑われる場合、カードの持ち主はどういった対応をすればいいのか解説していきます。
01 本当に身に覚えのない請求なのか再確認
人間の記憶というのは曖昧なもので、自分でクレジットカードを利用したことを忘れてしまっている可能性があります。
特に明細上では、実際に利用した店舗の名前ではない業者名で引き落としがかかっていることもありますので注意が必要です。
また、家族や同居人など身近な人が無断で利用していたというケースも想定されます。
この場合は、管理不行き届きということになり契約者の責任になります。
そうなると当然、補償を受けることはできないので、改めて自分のカードの管理を徹底したいところです。
02 契約しているカード会社に連絡を取カードの利用を停止
自らに非がなく、不正利用されていると考えられる場合はすぐにクレジットカード会社に連絡してカードの利用を停止してもらいましょう。
不正利用があった旨を伝えれば、カード会社も調査を開始してくれます。
また、カードの利用から60~90日経過した後では補償を受けることができないので注意しておきましょう。
最低でも月に一度くらいはカードの明細をチェックする習慣を身につけたいものです。
03 警察に届け出る
クレジットカード会社に連絡して不正利用の被害拡大を防いだ後は、場合によっては警察に届け出る必要があります。
警察に紛失届や盗難届が出されているカードが不正利用されたとしても、元の持ち主に責任は問われないということが法律で決まっています。
そのためクレジットカード会社に連絡する際には、警察に届け出る必要があるか確認してみてもいいかもしれません。

このような流れになっています。
当然ですが補償制度とはいっても、どのような条件でも補償してくれるというわけではないようですね。
上述したように補償制度には対象外とされる項目もあり、以下の場合については、カードの持ち主自身に支払いの義務が生じます。
暗証番号が必要な取引
家族・代理人の利用
自宅・勤務先のパソコンからの利用
不正利用から60~90日経過している
例えば、会社のパソコンでネット通販などを利用してカード情報をパソコンに残してしまい、そのカード情報で会社の誰かが利用した場合は、カードの持ち主が支払いをするという事です。
会社や自宅などの共用パソコンでクレジットカード情報を入力する際は注意するようにしましょう。